こんにちわ。sakuranokiiです。
前記事に引き続き、海外留学に興味がある博士課程の疑問や悩みに答えていこうと思います。
本記事で回答する疑問は下記です。

日本の研究室と海外の研究室ってどんな違いがあるの?
筆者は博士課程時代にドイツの研究室に短期留学しましたが、日本と海外の文化の違いは研究室生活にも色濃く影響していました。
筆者もそうでしたが、多くの方にとって海外研究室生活は日本とは大きく異なる生活になります。
環境の変化が大きく、筆者も留学したばかりの頃は気疲れすることが多かったですね。
初めての留学を控えた博士課程の方はそんな海外ラボでの新生活に不安もあると思います。
その不安を解消するには、あらかじめ日本と海外ラボの違いを把握しておくのが良いですよ。
というわけで、本記事の内容は下記です。
●テーマ
留学経験者の筆者が実際の経験に基づいて日本と海外の研究室の違いを解説する
●主旨
日本と海外の研究室の違いを予習をすることで海外での新生活への不安を軽減してほしい
●読んでほしい人
留学に興味がある博士課程、留学予定の博士課程
教員が少ない
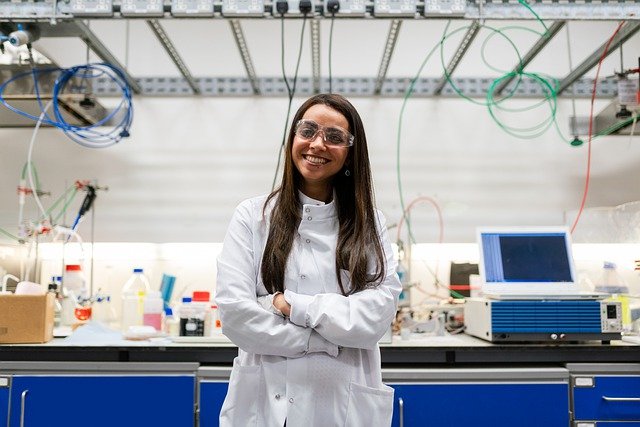

日本と海外の研究室の一番の違いって何?
日本と海外ラボの一番の違いは「大学教員の人数が少ないこと」です。
日本の研究室では教授、准教授、助教と教員は大体3~4名在籍しているのが普通ですよね。
一方で、海外の研究室では基本的に教授1名しか教員はいません。
教員と学生以外だと、事務関係の仕事を担う秘書さんと、実験機器メンテナンスのために雇う技術者の方がいます。
秘書さんは日本でも雇いますが、技術者も雇うのは海外研究室の文化だと思います。
教員が1人しかいないと聞くと、「それだけで本当に学生の指導ができるの?」と疑問に思うかもしれませんが安心してください(笑)。
次節で解説する日本と海外の違いが、教員がほぼいなくても研究室が回る大きな要因です。

筆者の訪問先の研究室は珍しく講師の先生もいました。教授が多忙な方でほとんどラボに居ない割に、学生の数は非常に多かったので、さすがにもう1人教員が必要だと考えたのかもしれませんね、
博士課程の学生が多い


教授1人で学生全員の面倒って見れるの?
教授1人でも学生の面倒が見れる理由は「博士課程の学生が多い」からです。
博士課程の学生なら自分の面倒は自分で見れるし、修士や学部生の指導もできます。
博士課程の学生がメインの研究室だからこそ教員1名でも問題ないというわけです。
このようにドクターの学生が多い点は海外と日本の研究室の代表的な違いの1つですね。
筆者が訪問した研究室は極端で9割が博士課程の学生でした(笑)。
噂には聞いていましたが、海外の大学院では博士課程まで進学するのが当たり前であると再認識しましたね。
内部進学だけでなく、世界中の大学院から博士課程の学生が集まっているのも海外研究室(特に世界的に有名なラボ)の特徴だと思います。
博士課程の学生が多いがゆえに、普段から学生間の議論が活発で、実験台の前でディスカッションしている学生たちをよく見かけましたよ。
また、週1で行う研究進捗会は学生のみで実施しており、教員なしでも十分成り立っていました。
博士課程の学生が中心に構成される海外大学院のレベルの高さに、初めて留学をされた方は驚くと同時に焦りを感じるかもしれませんね(笑)。
博士だらけのレベルの高い環境を活かして留学中も研究を頑張れば、帰国後には一回り成長していると思いますよ。

博士課程の学生が多ければポスドクも多いのが海外研究室の特徴です。海外では多くのドクターが卒業後にポスドクとして別の研究室に就職するのでそうなるのでしょう。多い研究室だと10人以上のポスドクを雇っているところもありますよ。
早く来て早く帰るが普通


博士課程の学生が多いのなら、ほとんどの学生が遅くまで実験しているの?
博士課程の学生は論文を書くために人一倍実験しないといけません。
日本では夜10時~11時ぐらいまで実験することが普通かと思います。
博士の多い海外研究室ならなおさら夜遅くまで灯りがついていそうですね(笑)。
ですが、意外にも海外研究室の学生は日本と異なり皆早く帰ります。
筆者が留学した研究室では皆大体7時~8時ぐらいには帰ってましたね。
プライベートな時間も大切にするのが海外研究室の特徴です。
皆早く帰りますが、その分朝早く来ているので実験量が少ないわけではありません。
また、海外研究室は上節で述べたように機器メンテナンスの技術者を雇うなど、学生が実験に集中しやすい環境が整っています。
その結果、短時間でも効率よく実験できるので研究成果もちゃんと出ています。
筆者も留学中は皆に合わせて朝型の研究室生活を過ごしていました。
頭が冴えている時間が日本よりも長く、効率よく研究を進められた実感がありましたよ。
博士課程の方は海外研究室の朝型スタイルを取り入れてみてはいかがでしょうか?

留学中に筆者の面倒を見ていた中国人ドクターは珍しく夜型でした。お昼前に来て日付が変わるまで実験するスタイルの方でしたね。何事にも例外はあります(笑)。
その他の違い一覧


他にも日本と海外研究室の違いってないの?
ほかにも細々とした違いは色々ありましたので、最後にまとめてご紹介します。
筆者が訪問したラボ特有の文化かもしれませんが、ご参考までに。
●研究室がめちゃくちゃ広い
・建物の1フロアがまるまる1つの研究室で、部屋数で言うと10部屋以上はある
・広いおかげで実験スペースや実験機器もたくさんあるので実験がはかどる
●戸締りが厳重
・広いためか誰もいない部屋ができやすいので移動するたびによく戸締りをしていた
・鍵が日本と形式が違うので慣れるまで苦労した
●実験室内にはBGMが流れている
・スピーカーが置いてあり誰かのお気に入りの音楽やラジオが常に流れていた
・デスクワークに集中するための静かな部屋は別にある
●大量の飲料水・お酒・お菓子が置いてある
・食糧庫みたいな部屋があり、ちょっとしたパーティをするときに利用していた
・パーティー以外の時でも有料で水やお酒などが買えた
●研究室全員の誕生日を祝う
・ラボメンバーの誕生日では皆でケーキを食べて祝っていた
・ただしケーキは誕生日の人が用意する文化だった
●教授が定期的に話に来る
・たまに教授が各部屋を巡回し学生に話かけて困っていることがないか聞いていた
・日本の教授よりかなりフレンドリーに接してくれる(教授でも名前呼びOK)

逆に日本と変わらない部分を見つけるのも面白いです。例えば、最近の論文を紹介する抄録会は海外研究室でもやっていました。あとは、食堂のメニューに不満があるところも同じですね(笑)。
まとめ
いかがでしたでしょうか?本記事の内容をまとめると下記のとおりです。
●日本と海外ラボの一番の違いは「大学教員の人数が少ない」
●「博士課程の学生が多い」も代表的な違いの1つ
●海外研究室の学生は日本と異なり朝早く来て早く帰る
●その他にも「研究室が広い」「実験室内にBGMが流れている」など様々な違いがある
留学の醍醐味の1つは日本と海外の研究室の違いを楽しむことだと筆者は思います。
もちろん最初はその違いに戸惑うかもしれません。
ですが、日本と海外の違いを知れば知るほど、自分の視野が広がっていくのを感じます。
日々の生活を通じて自分の中の世界が広がっていく感覚は留学しないと味わえない貴重な経験です。
異なることを心配するのではなく楽しむ気持ちを持てば、有意義な留学生活を過ごせると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
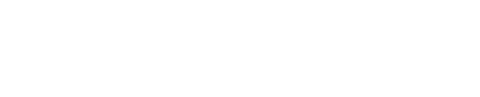

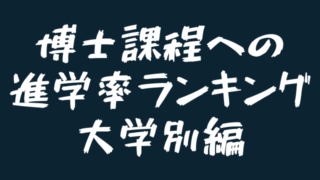
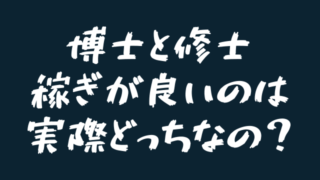
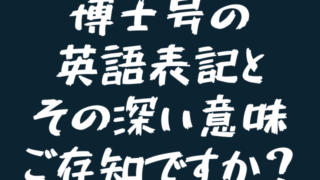


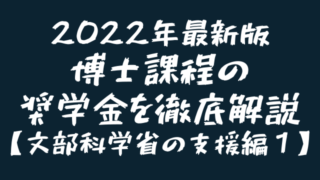
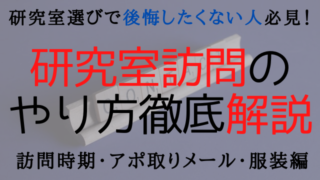



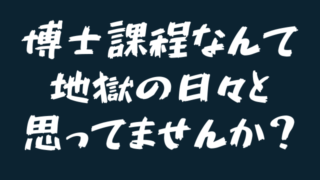

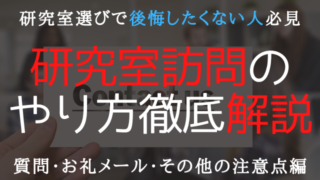

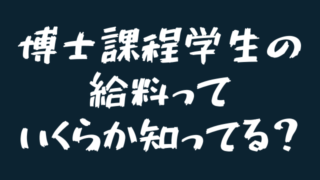





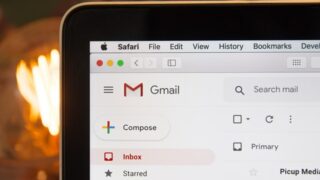
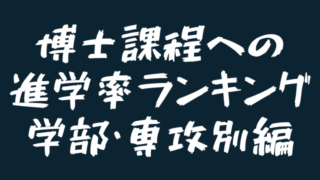



コメント