こんにちわ。sakuranokiiです。
博士課程に興味がある大学生の方はこんな不安をお持ちではないでしょうか?

博士課程に興味はあるけど博士が企業に就職するのは大変らしい…
ちゃんと就職できるか不安で進学するのが怖い…
博士課程の学生は就活で苦労するという話は巷でよく聞きますね。
ですが、過去記事でも解説したように博士課程に進学しても就職が不利になることはないです。
適切に就職に向けた対策をすれば普通の学生より勤勉な博士課程の学生が就職できないわけありません。
本記事では、その「博士課程がすべき適切な就活対策」について深堀したいと思います。
文部科学省発行のレポート「民間企業における博士の採用と活用」では、製造業の研究開発部門を中心に様々な業界・規模の企業を対象とした博士採用に関するインタビュー結果がまとめらています。
本レポートでは「民間企業が求める人材の特徴」「博士人材の能力に対する印象」「博士採用時に重視する点」といった企業への就職を目指す博士課程学生に有益な情報が報告されています。
上記の情報に加え、筆者自身の就職経験も基にして「受かる博士」と「落ちる博士」の違いを考察し、その違いから分かる博士課程の就活テクを伝授いたします。
というわけで、本記事の内容は下記です。
●テーマ
博士号取得者の筆者が調査結果と実際の経験に基づき博士課程用の就活対策を伝える
●主旨
博士課程に興味はあるけど就職できるかが心配で進学をあきらめる人が減ってほしい
●読んでほしい人
博士課程を目指している大学生
結果よりも過程をアピールしよう


一番重要な博士課程の就活テクって何?
筆者の考える最も重要な博士の就活対策は「研究結果よりもその結果に至る過程を積極的にアピールすること」です。
今回調査した文献では企業が採用時に重視する点として下記記述がありました。
博士課程における研究業績そのものではなく、研究に取組む際の姿勢や方法論、研究プロジェクトにおける本人のコミットメントの度合いが重視されている
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 民間企業における博士の採用と活用
つまり、企業が就職面接で知りたいのは研究成果よりもその過程なのです。
上記をもとにした「落ちる博士」と「受かる博士」の違いは下記です。
●落ちる博士
就職面接であるにもかかわらず学会のように研究の成果報告をしてしまう
●受かる博士
研究成果よりもその成果を得るために自分自身がどう考えどう行動したかを積極的に話す
研究活動の苦労話をすることで、自分の課題発見力と課題解決能力をアピールできるのです。
実際、筆者も就職面接の質疑応答の際に自分がどういう経緯でこの研究テーマを立ち上げたか、どのデータを出すのに苦労したかといった裏話もしましたが、そのときは議論が盛り上がり手ごたえを感じましたね。
博士は普通の学生よりも苦労して素晴らしい研究成果を出している人が多いと思いますが、教員の指示通りに動いただけの学生と企業側に判断された場合は残念ながら採用されません。
せっかくの研究成果を無駄にしないためにも、博士は成果に至るプロセスも遠慮せずアピールしましょう。

今回調査した文献の「民間企業が求める人材」の1つに「国際的な競争下で経験を積んだ人材が好まれる傾向にある」との記述がありました。修士で海外留学する人は極まれなので、海外留学の経験がある博士は就活で海外研究経験をアピールすると差別化もされて好印象だと思いますよ。
話す内容よりも話し方を工夫しよう


博士課程がなりがちな「落ちる博士」の特徴って何?
2つ目の就活テクは「話す内容よりも話し方を工夫すること」です。
今回調査した文献中、企業の博士人材の能力に対する印象および採用時に重視する点としてそれぞれ下記記述がありました。
博士は修士と比べると、プレゼンテーション能力は高いが、コミュニケーション能力や物事を平易な言葉で伝える力に問題のある場合が見受けられる
社会における自身の研究の意義や位置付け、研究内容のオリジナリティや新規性について自分の言葉で説明できる人材が望まれている
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 民間企業における博士の採用と活用
つまり、企業は相手に伝わる言葉で自分の言いたいことを伝える能力を重視しています。
上記をもとにした「落ちる博士」と「受かる博士」の違いは下記です。
●落ちる博士
どんな相手に対しても専門用語を多用して説明したり、論文の文章のような小難しい表現で会話する結果、相手に言いたいことが伝わっていない
●受かる博士
相手に合わせて物事の言い回しを工夫する
学会発表では許されるプレゼンでも、就職面接では通用しないことを理解しましょう。
特に博士課程の学生は研究室生活が長いので、専門分野が同じ人・アカデミック職の人との会話に慣れ過ぎた結果、気を抜くと上記の「落ちる博士」になりがちです。
就職面接では基本的に自分と同分野の面接官はいないことを想定して、かみ砕いた表現で自分の研究の意義を伝えるようにするべきです。
また、入社後も同様に様々なバックグラウンドの方と仕事をすることになるので、相手に合わせた物事の伝え方を自分なりに考えるスキルは重要です。
実際に筆者は最終面接の質疑応答の際、1番最初の質問が素人にも分かる表現で研究の面白さを説明してほしいという内容でしたので、平易な言葉で物事を説明する力は重要視されていると思います。
このように相手基準で行動するという姿勢はサラリーマンとして重要な心構えですので、学生のうちから身に付けておくと良いですね。

今回調査した文献の「採用時に重視する点」の1つに「自社の経営理念を実現できる人物であるか、社風に合う人間性を有しているか」との記述がありました。ESや面接で経営理念に対する共感や、社風に合う人間性であることが分かるエピソードがあればぜひアピールしましょう。
専門性だけでなく研究者の素養もアピールしよう


「落ちる博士」と「受かる博士」に分かれるありがちな要因は何?
3つ目の就活テクは「専門性だけでなく研究者としての素養もアピールすること」です。
今回調査した文献中、企業の博士人材の能力に対する印象および採用時に重視する点としてそれぞれ下記記述がありました。
博士課程の研究活動を通して培った専門性もさることながら、専門性を身につけられるという能力自体も重要視されている。また、専門性を身につける中で得た論理思考や事象を体系化する能力にも期待がもてる
博士としての専門性を求めると同時に、他の能力も修士より高いことを期待する企業もある。他の能力とは、研究に関する能力(研究力、実験スキル、自身で仮説構築・検証する等)や、製品開発・新規事業などで新しいものを生み出す際に必要となる能力(創造性、アイディア、将来予測、自身で将来を開拓する 等)、その他汎用性が高いスキル(コミュニケーション、プレゼンテーション、リーダーシップ 等)など多岐に渡り、求められる能力の重きは、企業が置かれている状況によって異なっている。
博士として最新の専門知識を有していることに加え、原理原則や根源的・汎用的な知識等、基礎的な素地のある人材であることも期待されている。
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 民間企業における博士の採用と活用
よく聞く話ですが、やはり企業は博士に専門性の高さだけでなく、一人前の研究者としてふさわしい研究遂行力や見識の広さを求めているのです。
上記をもとにした「落ちる博士」と「受かる博士」の違いは下記です。
●落ちる博士
専門分野を極めることに注力してしまい、日本企業が求める汎用性が高く使いやすい人材から遠ざかっている
本当は総合力の高い学生なのに自己アピールが足りず、専門バカの博士と判断されてしまう
●受かる博士
日本企業がジェネラリストを好むことを把握しているので、専門分野にとらわれず自主的に異分野の勉強も行う
研究室生活で「自ら課題を設定し解決する」「新テーマに挑戦する」「学生のリーダーとして振舞う」といった企業が求める能力を鍛える行動を意識的にとり、それを就活の際に適切にアピールできる
意識的にやった方が効果的なことは確かですが、筆者の経験上、博士課程で真っ当に努力していれば企業が求める「専門性以外のスキル」も大なり小なり自然と身に付くのではないでしょうか。
なので、上記の「落ちる博士」と「受かる博士」に分かれる主な原因はアウトプットの上手さにあると思います。
企業が評価するポイントをしっかり押さえたエピソードを用意し就活でアピールすれば、思ったよりも簡単に「受かる博士」になれますよ。

今回調査した文献の「企業が求める人材」の1つに「周囲を巻き込みながら事業を推進できる」との記述がありました。企業に入ると分かりますが、企業の研究は大人数で協力して進めますので研究職といえどもチームワークはとても重要です。他人と協力しながら研究を進めた経験(共同研究など)があれば、良いアピールポイントになると思いますよ。
意志の強さだけでなく柔軟性もアピールしよう


「落ちる博士」がやりがちな失敗って何?
最後の就活テクは「意志の強さだけでなく柔軟性もアピールすること」ですね。
今回調査した文献中、企業の求める人材として下記記述がありました。
民間企業の研究開発分野は、社会の状況や顧客のニーズに応じて変更を余儀なくされるため、企業の研究開発者は1つの専門性を入口としながらも、自身の専門分野に固執せず、関連分野への幅広い知識や興味が期待されており、研究開発分野の変更に対して臨機応変に対処できる柔軟性が求められる
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 民間企業における博士の採用と活用
つまり、企業は顧客ファーストで研究を進められる人材が欲しいのです。
上記をもとにした「落ちる博士」と「受かる博士」の違いは下記です。
●落ちる博士
「一度決めたことは最後までやり通す」「周りに流されず自分の意志を貫ける」と言うと聞こえがいいが、それだけをアピールするのは融通がきかない人間と思われるので落ちる博士がやりがちな失敗
●受かる博士
過度な意志の強さは時にビジネスの障害になるので、融通が利く人材の方が好印象なことを知っているので、自分の専門分野から離れる仕事であっても引き受けるし、顧客ニーズに対応するために新たな知見を手に入れる努力を惜しまない柔軟性を意識的にアピールする
柔軟性をアピールする1例として、面接で「どんな研究をしてみたいですか?」と質問されたケースを考えてみましょう。
「〇〇が私の専門なので〇〇に関係する仕事をしたいです」と専門性が高い博士はついつい答えがちですが、それは「落ちる博士」の答え方です。
柔軟性の大事さを知っている「受かる博士」なら「できれば〇〇が私の専門なので〇〇に関する仕事であれば嬉しいですが、どんな研究テーマであれ博士課程で培った研究遂行力を活かせば御社に貢献できます」と答え、柔軟性をアピールします。
大学とは違い企業の研究は自分のやりたいことではなく、相手(顧客・企業)がやりたいことを実現するのが最重要です。
その研究目標の違いを念頭において、就活での受け答えを工夫してみてはいかがでしょうか?

今回調査した文献の「博士人材の能力に対する印象」の1つに「博士課程修了者は未だマイノリティであり、社内に新しい風を吹き込むための異質な人材として、また、これまでに他の社員が保持していないリソース・ネットワークや、新しいアイディアの提供者としての価値が見出されている」との記述がありました。柔軟性は大事ですが、博士が没個性的になるのを企業は望んでいないようです。顧客のためになるのなら博士は自分なりの意見を積極的に発言しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?本記事の内容をまとめると下記のとおりです。
●博士向け就活対策その1は「研究結果よりもその結果に至る過程をアピールすること」
●「受かる博士」は成果よりもその成果を得るために自分がどう考えどう行動したかを話す
●博士向け就活対策その2は「話す内容よりも話し方を工夫すること」
●「受かる博士」は相手に合わせて物事の言い回しを工夫する
●博士向け就活対策その3は「専門性だけでなく研究者としての素養もアピールすること」
●「受かる博士」は研究室生活で「自ら課題を設定し解決する」など企業が求める能力を鍛える行動を意識的にとり、就活の際にアピールする
●博士向け就活対策その4は「意志の強さだけでなく柔軟性もアピールすること」
●「受かる博士」は専門分野から離れる仕事であっても引き受けるし、顧客ニーズに対応するために新たな知見を手に入れる努力を惜しまない柔軟性をアピールする
博士課程の学生は研究に没頭するあまり就活対策をおろそかにしがちだと思います。
思い返せば筆者自身もそうでしたね(笑)。
ですので、本記事を読んで就活対策の準備を進めている方はそれだけでも偉いです。
きっと本記事の対策も実行に移すでしょう。
そんな偉い貴方が博士課程に進学して就活に苦労する可能性はとても低いと思いますよ。
ぜひ博士課程への進学を前向きに検討してください!
以上、ご参考になれば幸いです。
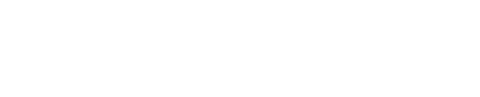
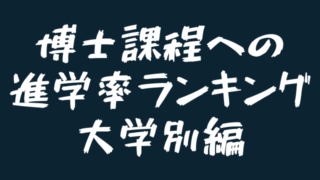
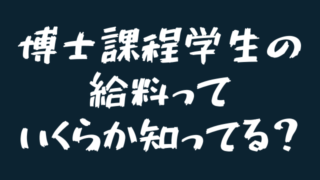
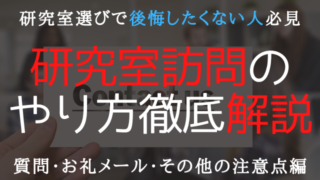







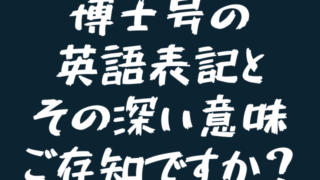
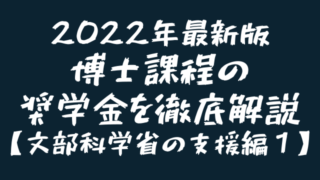
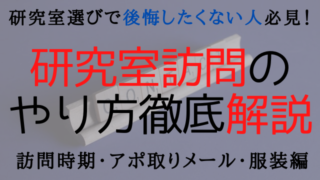

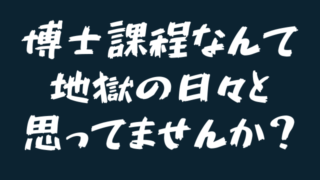


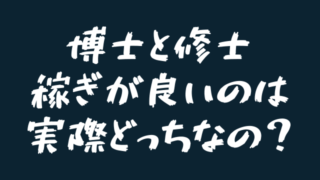







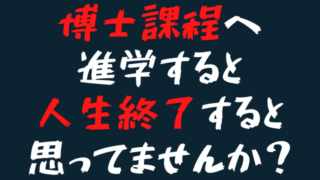



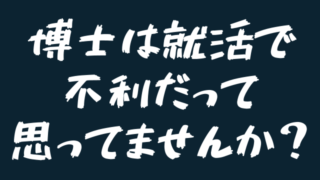
コメント