こんにちわ。sakuranokiiです。
有機合成化学系の研究室に在籍している大学院生の方はこんな疑問をお持ちではないでしょうか?

企業で行う有機合成の研究って大学とはどう違うの?
企業の研究は大学とは目的が違うため業務内容に異なる部分は多々あります。
有機合成化学の研究でもそれは同様で、重要視されるスキルは大学の頃とは変わってきます。
企業で有機合成化学の仕事をしたい大学院生の方は大学時代からそのスキルを意識して鍛えておくと即戦力になれると思います。
というわけで、本記事の内容は下記です。
●テーマ
有機合成化学の現役研究職である筆者が実際の経験に基づき、大学と企業で有機合成の仕事にどんな違いがあるか解説する
●主旨
企業で有機合成化学の仕事をしたい大学院生に早い段階から企業で重要視されるスキルを鍛えておいてほしい
●読んでほしい人
有機合成化学の研究職を目指している大学院生
ターゲットはお金になる分子


企業でターゲットにする分子って何?
まずは、企業で合成する分子は何か説明します。
ずばり「お金になる分子」がターゲットです。
具体的に言うと下記のような分子です。
●顧客がほしい分子
大学では珍しい性質の分子なら価値があるが、企業では顧客の望む分子でないと価値はない
●利益が出る分子
顧客が欲しい分子でも赤字になるなら作る意味はない
●他社特許に抵触しない分子
特許NGの分子はそもそも売り物にならない
上記3つの要素を最低限満たさないと「お金になる分子」にはなりません。
したがって、企業で合成ターゲットを考える際に重要なスキルは下記です。
・顧客ニーズを把握する情報収集能力
・できるだけ安価な原料で目的物を提案する能力
・特許抵触リスクを正確に調べきる能力
特に、原料コストの感覚は大学の頃から鍛えやすいです。
どういった構造は安く、どういった構造は高いのか意識して試薬を買うことでコスト感覚が磨かれます。
そして、安い原料からターゲットを作る習慣を身に付けましょう。
また、大学の頃に比べて主体的に情報収集しないとターゲットは決められません。
自分から相手に働きかけて必要な情報を手に入れる姿勢を学生時代から意識しましょう。

有機合成に限らず技術系なら勤務中は作業服を着用することになります。出退勤は私服で良いので新人研修以降スーツを着る機会はほとんどないですね。そのうえ最近はコロナの影響で出張もないのでもう何年もスーツを着ていないです(笑)。
工場で作れないと意味がない


ターゲットの合成ルートを考える際の注意点ってある?
ターゲットが決まったら合成ルートの検討を開始します。
合成方法は何でもいいわけではなく、工場で実施可能な合成方法でないといけません。
研究の段階から量産する上で好ましい合成ルートに仕上げておくことが必要です。
工場で実施するのに好ましい合成方法の具体的な例は下記です。
●反応温度は高くても100℃強
加温は実験室のようなオイルバスではなく温水や水蒸気で実施するため100℃よりも高温条件は作りにくい
●過度な発熱や発泡を伴わない反応
実験室スケールでは何とかなっても、工場スケールでは過度な発熱や発泡を伴う反応は安全上の障壁が大きいため避けるべき
●環境や人体に有害な溶媒を使わない反応
環境や人体に有害な溶媒は法律や条例により厳しく管理されているため避けるべき
●空気中で非常に不安定な分子を扱わない反応
グローブボックス中でないとうまくいかない反応は工場では実施困難
●副生成物があまり出ない反応
精製の手間が増えると時間も人件費もかかり利益率が下がるし、品質管理も大変になるため避けるべき
●ステップ数の少ない合成ルート
ステップ数が多いと上記と同じく採算がとりにくくなり品質管理も大変になる
●抽出回数は1~2回、水洗回数もできるだけ少なくする
工場での分液は下層を下の階もしくは隣の窯に移して取り除くため、何度も抽出するなら広大なスペースとたくさんの窯が必要になり非現実的
工場スケールだと分液1回に1時間以上かかるので、時間効率の意味でも分液回数が最小限で済む抽出溶媒の選択が重要
●精製は再結晶か蒸留
カラムは実験室スケールでは便利だが工場スケールでは実施するのが大変でコストがかかるので避けるべき
大学では基本的にカラムで精製する方が多いと思いますので、特に精製方法の検討については企業に入ってから悩まされるところです。
大学時代から再結晶や蒸留による精製にも習熟しておくことをお勧めします。
また、原料の入手容易さも合成ルートを決める上で重要です。
上節で安い原料を使うことが採算を取る上で重要と書きましたが、安価な原料はすぐに大量に手に入るため工業化に向いている意味でもメリットがあるのです。
したがって、企業で合成ルートを考える際に重要なスキルは下記です。
・「これは工場で扱える化合物か?実施可能な操作か?」と想像する能力
・安価で入手容易な原料で合成ルートを構築する能力
大学時代から工業化可能な合成ルートに縛られる必要はないと思います。
ですが、企業でも有機合成をしたいのなら、学生時代から安全かつ簡単に行える合成ルートを提案する練習はしておくべきですよ。

研究職に就いても工場実習で現場の様子を勉強する機会はあります。研究室で行う実験とはまるで違うので面白いですよ。現場の有機合成への考え方を知ることで有機合成の研究職としての視野も広がりますね。
品質の安定性が命
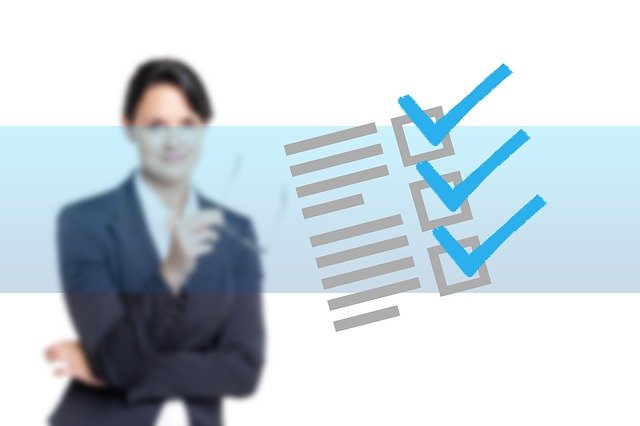

合成しているときの注意点って何かあるの?
合成ルートが決まり上司の許可も得られたら合成スタートです。
合成の際に気をつけることは「品質を安定させること」です。
企業は商品として分子を作りますので、商品の品質を担保するうえで各分子に品質規格(不純物含有量や水分量など多項目)を設定し、それを遵守する必要があります。
スペックアウトした分子は不良品ですので顧客は買ってくれないし、信用の喪失にもつながります。
つまり、合成反応の再現性をとることは事業の継続に影響するので非常に重要なのです。
チャンピオンデータを載せればOKの論文とは大違いです(笑)。
したがって、合成の際には下記点に気をつけています。
●各工程で行った操作を詳細に記録する
完璧に再現性をとるためには細かい操作まで一致させる必要がある
使用した実験器具、攪拌速度、滴下にかけた時間、分液回数、分液に使用した溶媒量や水の量、再結晶条件、蒸留条件など
●各工程で起こった現象を詳細に記録する
再現性がとれなかった際の原因考察のため必要
反応溶液の温度変化や色の変化、沈殿物の発生状況、分液性の良し悪し、結晶性の良し悪し、初留と本留の沸点、各精製過程でのマスバランス変化など
●使用原料や各工程ごとの分析データを取得する
再現性がとれなかった際の原因考察のため必要
原料は使用前にGCやLCで分析し異常がないかチェックする(ロットが変わる場合は特に注意)
分析データは反応開始直後、反応途中、反応完結後、クエンチ後、分液前後(水層も)、再結晶前後(ろ液も)、蒸留前後(各留分すべて)で取得し、収率変化や不純物量変化を追跡する
上記全てを常に行うのが理想ですが、性能が本当に良いか分からない初期検討時は早く作って性能評価する方が重要ですので工程管理は最低限にすることが多いです。
材料の有用性が判明すれば、合成ルートを固めていくうえで厳重な工程管理を実施します。
工程管理は大変ですが、企業で有機合成を担当するなら必ず通る道です
したがって、企業で有機合成実験を行う上で重要なスキルは下記です。
・こまめに情報を記録する几帳面さ
・細かい変化も見逃さない観察眼
・各種分析方法の知識
大学時代から実験ノートに丁寧に情報を記入する習慣がある方は企業でも重宝されると思います。
観察眼はすぐには養われないので、普段の実験から反応系を注意深く観察する癖をつけましょう。
また、合成だけでなく分析の知識も企業では重要です。
NMRを始め、GCやLC、質量分析の測定方法やノウハウは身に付けておきましょう。

筆者のような有機合成の研究職は化学薬品を扱う実験がメイン業務ですのでテレワークはできないですね。一方で品質保証や解析がメインの研究職の方はテレワークもしています。研究職でテレワークができるかは業務内容によりますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?本記事の内容をまとめると下記のとおりです。
●企業でターゲットにするのは珍しい性質の分子ではなく「お金になる分子」
●企業で目指す合成方法は工場で実施可能な安全かつ簡単に行える手法
●企業では反応の再現性が事業の継続に影響するので非常に重要
●学生時代から情報収集力、コスト感覚、簡便な合成ルート提案力、観察眼、分析の知識を身に付けておくべき
商売として有機合成を行う企業では様々な制約があります。
企業特有の制約をクリアするために必要なスキルが企業で有機合成化学を担う研究職には求められます。
これらのスキルは研究室生活の中でも鍛えられます。
一長一短には身に付かない能力なので、日々の積み重ねが大事です。
本記事で書いたことを少しずつでも実践すれば、企業に入ってすぐ重宝される人材になれると思いますよ。
以上、ご参考になれば幸いです。
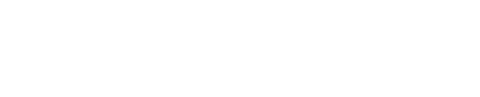

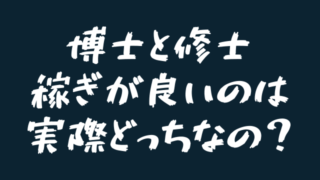
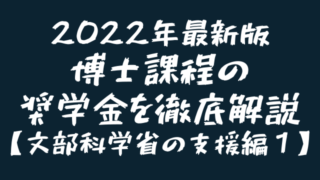



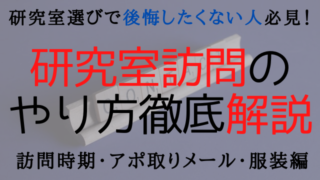
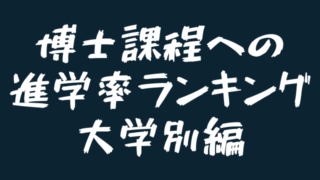


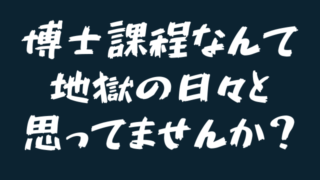


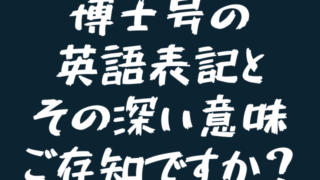

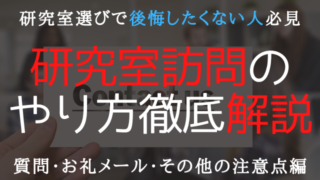

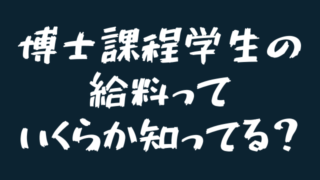
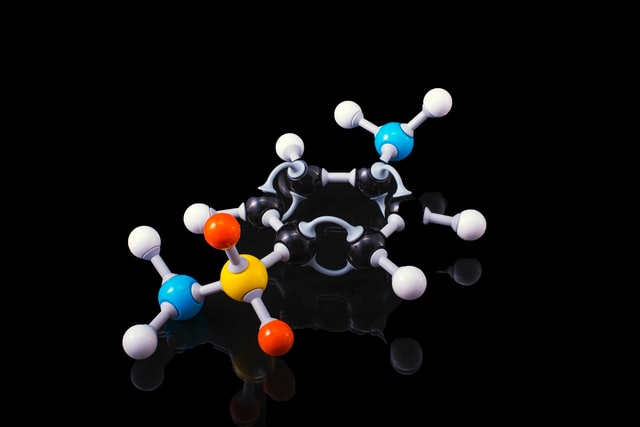




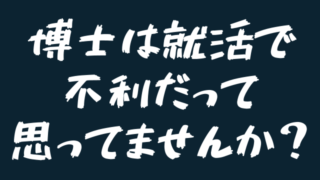
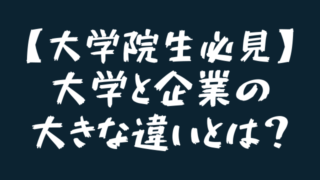



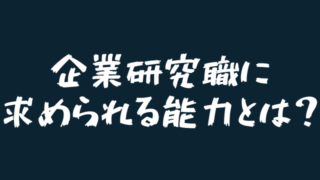
コメント